「ひとりでしにたい」第5話から、「保険の見直し」を終活の視点で考えてみませんか。
感情で解約・乗り換えを決める前に、数字と書面をそろえるだけで、後悔は大きく減らせます。
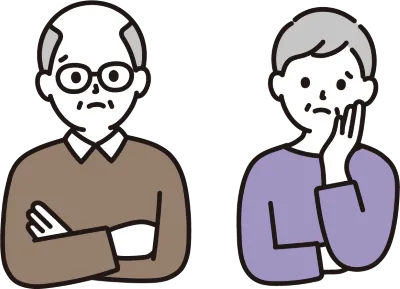
目次
まずは“いまの契約”を見える化
最初にやることはシンプルです。
保険証券やマイページを開き、次の項目を一枚のメモにまとめます。
- 契約者/被保険者/受取人
- 保険の種類(終身・定期・医療・がん等)と保険期間
- 月額保険料・次回更新や満期の時期
- 現時点の解約返戻金の目安
- 解約以外の選択肢(減額・払済・延長保険・特約の付替え など)
ここまで整うと、「何を残して、何を軽くするか」の判断が一気にしやすくなります。
あなたの目的は?
保険は“目的のための道具”です。たとえば、
- 医療費・がん治療費の備え
- 葬儀費用(数十万円〜)の確保
- 特定の人に現金を遺す(生命保険金)
この目的に合っていれば見直しは調整(減額・特約整理)で済むことが多く、合っていなければ乗り換え・終了が候補になります。
解約・乗り換えリスクを先にチェック!
解約・乗り換えの前に、次のリスクを確認してみてください。
- 解約で保障の空白が生じないか
- 高齢になって再加入が難しい商品ではないか
- 税金の確認:
・死亡保険金は相続税のみなし相続財産(非課税枠:500万円×法定相続人)。
・解約返戻金は一時所得等として所得税・住民税がかかる場合あり。
数字は契約内容で異なるため、必要に応じて税理士に確認してから判断すると安心です。
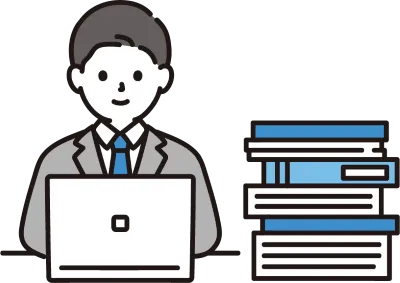
生命保険と遺言・死後事務の“つなぎ方”
終活では、「お金の流れ」と「手続きの流れ」を事前に結んでおくと実務がスムーズです。
- 受取人を変えたい場合は保険会社で変更手続を行います(遺言でも受取人を変更できますが、保険会社によって対応が異なる可能性があります)。受取人を家族以外にすることは契約上可能な場合がありますが、約款や同意要件に従ってください。
- 税務:死亡保険金は民法上は受取人の固有財産ですが、相続税ではみなし相続財産として扱われ、非課税枠(500万円×法定相続人)の適用可否を確認します。
- 遺留分との関係:一般に保険金は遺留分算定の基礎に含めませんが、保険金が相続財産に比して著しく多額など事情によって考慮される可能性があります。
- 死後事務委任契約:死亡届・葬儀・公共料金やサブスクの解約・関係者への連絡などは委任で実行できます。一方、預金払戻しや相続手続は相続人(または遺言執行者)の権限が必要です。役割を書面で分けて明示しておくと実務がスムーズです。
- エンディングノートは法的効力なし。最終意思(遺産配分や葬送方針)は遺言で、当日の段取りは死後事務委任で残す——この二層構えがお勧めです。
今日からできる“小さな5つ”
- 保険の一覧メモを作る(契約者/受取人/種別/返戻金目安/更新・解約日)。
- 受取人指定を最新化し、遺言・死後事務委任と整合させる。
- 葬儀費用の目安を決め、必要なら小口の保障で補う。
- 公共料金・サブスク・デジタルアカウントの停止リストを作る。
- 判断に迷う箇所だけ、保険会社(数字)→税理士(税務)→行政書士(書類・設計)の順で外部連携する。
よくある質問(短答)
Q. 独身なので死亡保険はいりませんか?
A. 必要なのは「目的次第」です。葬儀費用の確保や、金銭を渡したい相手が明確なら検討価値があります。目的がなければ減額や終了も選択肢です。
Q. 受取人を家族以外にできますか?
A. 可能です。指定は生前にご本人が行います。指定の可否・方法は契約ごとに異なるため、保険会社で手続要件をご確認ください。
まとめ:感情ではなく、数字と書面で整えよう。
保険見直しは、終活の現実的な第一歩です。
現状の見える化→目的との整合→リスクチェックの三段階を踏み、必要な部分だけ専門家を活用しましょう!書類が整えば、残される方の負担は確実に軽くなりますよ。
📌行政書士ささき事務所では無料相談を受け付けております!

【平日】09:00~21:00【休日】09:00~18:00
24時間お問い合わせ可能!
確認次第すぐご連絡いたします

