介護保険内でのサービスでは保険外の訪問介護では、契約書の設計でトラブルが予防できます。
よくある質問を、すぐ使える条文例で整理しました。

目次
Q1.キャンセル料はどこまで認められる?
A1.消費者契約法の「平均的損害」の範囲で段階設定すれば有効。根拠(人員確保費・時間枠の機会損失・決済手数料)を数値化して社内保存。
条文例)解約料は当社に生ずる平均的損害の範囲で、7~2日前20%/前日50%/当日100%とします。平均的損害には人員確保費・時間枠の機会損失・決済手数料を含みます。
段階料+根拠メモが鉄則。数字の裏付けがあれば、運営指導やクレーム対応がスムーズです。
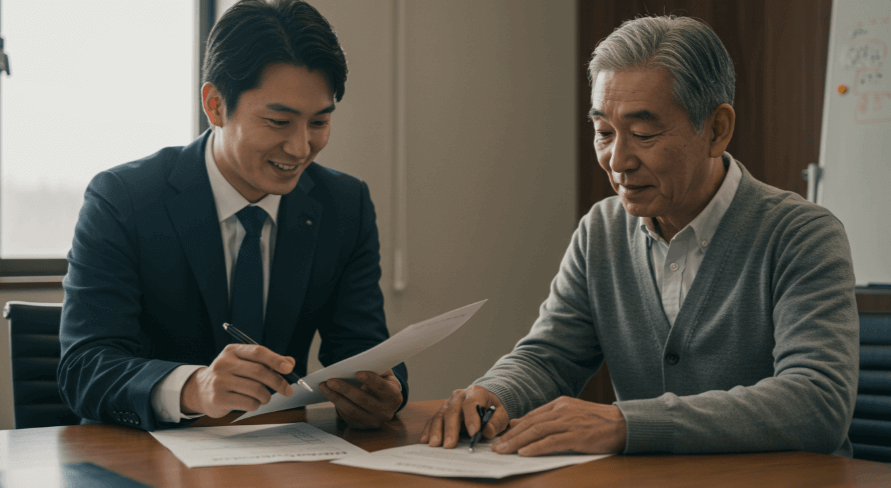
Q2.連絡なし不在・遅刻はどう扱う?
A2.一定の有料待機を明記し、超過は当日扱い。交通費は実費。
条文例)到着後○分は有料待機とし、以降は当日キャンセルとします。交通費は実費相当を請求します。
“何分待つか”“いくら発生するか”を数値で。現場の迷いを無くします。
Q3.責任限定(免責)はどう書けば安全?
A3.軽過失のみ上限、故意・重過失/生命・身体は除外。
条文例)当社の軽過失による損害の賠償上限は、当該月を含む直近3か月の対価総額とします。故意または重過失および生命・身体に関する損害には本上限を適用しません。
“除外を明記”がポイント。書かないと条項ごと無効リスクが上がります。

Q4.サービス範囲と医療行為の線引きはどうする?
A4.非医療の明記と禁止行為の列挙。
条文例)本サービスは医療行為の代替ではありません。創傷処置・注射・点滴・服薬内容の変更等は行いません。必要時は主治医へ連絡します。
“できる/できない”を分けるだけで誤解クレームが激減します。
Q5.個人情報(要配慮情報)の取り扱いはどうする?
A5.目的・保存期間・第三者提供・委託管理を具体化。
条文例)健康情報はサービス提供と安全管理の目的に限り利用します。保存期間は最終利用日から○年。委託時は秘密保持契約を締結します。開示・訂正・削除等の請求窓口は○○です。
“要配慮情報”は同意の質が命。書式にチェック欄を。
私がサポートできること

私は、理学療法士として10年以上現場に携わり、
医療・介護・福祉の現実を知る立場から行政書士として開業しました。
自費リハや保険外サービスでは、
「法律に触れないか心配」「契約書をどう作ればいいかわからない」
といった相談を多くいただきます。
行政書士として、私は次のようなサポートを行っています:
- 自費リハや外出支援サービスの契約書・同意書の作成
- 法律に基づくリスク回避のチェックと修正
- 利用者向け説明書・広告文の表現確認
- サービス運営全体の法的整備(免責・個人情報・運営規約など)
医療・介護・福祉の“現場を理解した法律支援”だからこそ、
机上の法解釈ではなく、実際に使える書類・説明の整備が可能です。
「現場を知る行政書士」だからこそ作れる契約書があります。
法律の理屈だけでなく、実際の運営に役立つ“生きた書類”で、現場を守り、リハビリ業界を支えていきたいと考えています。
📌オンラインの打ち合わせ不要!LINEでのやり取りだけで契約書を作成します!

【平日】09:00~21:00【休日】09:00~18:00
24時間お問い合わせ可能!
確認次第すぐご連絡いたします

