近年、保険外のリハビリや介護サービスに挑戦する事業所が増えています。
この記事では、現場の実情を理解したうえで、法律的にリスクを避けながら安心してサービスを始めるためのポイントをお伝えします!
※すぐに実務で使える「契約書雛形セット」をお探しの方は、こちらからご確認いただけます。
目次
自費リハ契約書が必要な理由 ~“効果への期待”がトラブルになる前に~
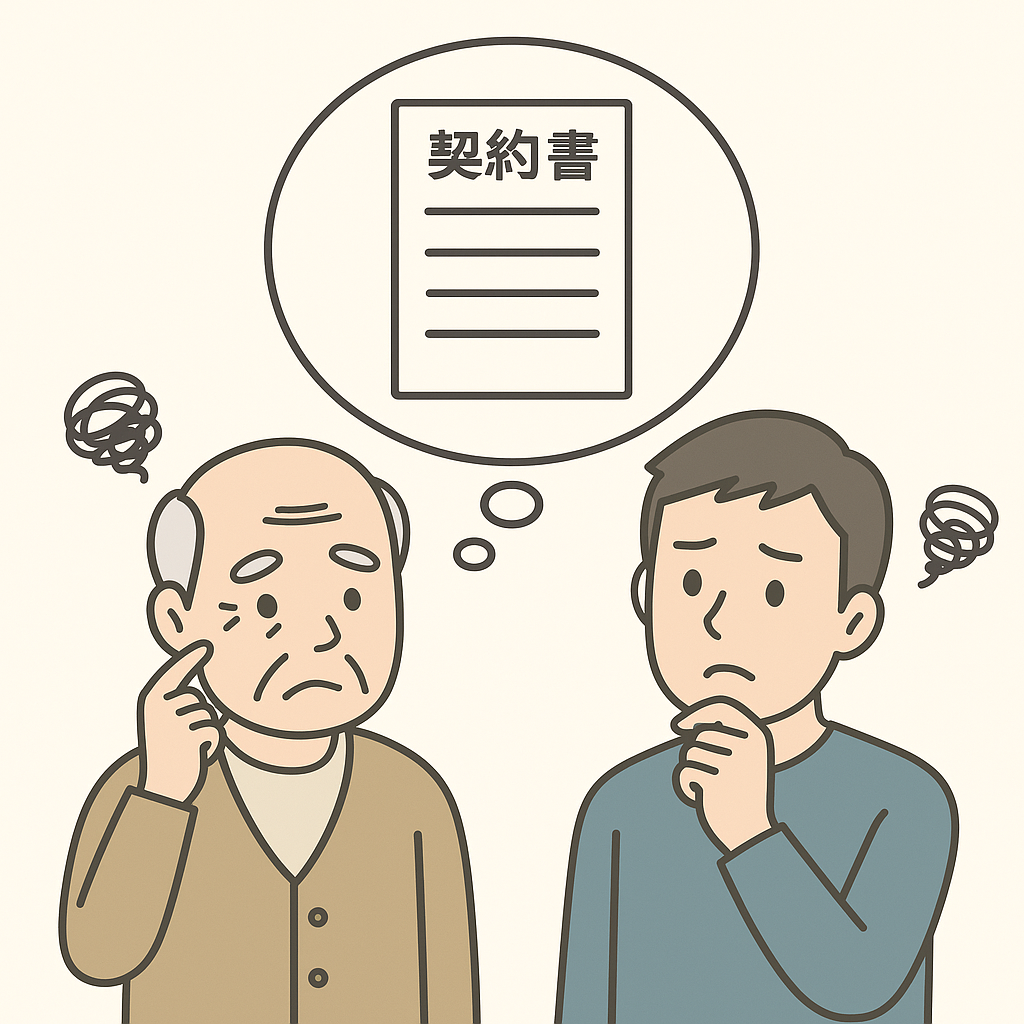
自費リハビリを利用される方の多くは、「効果のあるリハビリを受けて障害を治したい」という強い思いを持っています。
一方で、リハビリの効果には個人差があり、医学的にも“結果を保証できない”のが現実です。
この“効果への期待”のギャップこそが、トラブルの温床になります。
実際に現場では、
- 思ったように回復しなかった
- 施術が合わなかった
- 説明が不十分だった気がする
といった理由から、返金や損害賠償を求められるケースも少なくありません。
こうしたトラブルの多くは、「契約内容があいまいだった」「お互いの認識が違っていた」ことが原因です。
つまり、問題の本質はリハビリそのものではなく、合意形成の不足にあります。
リハビリの“効果”を信じて来られる方ほど、期待とのズレが起きやすいんです。
クレームに繋がらないためには、きちんとした説明と同意が必要になります。
そこで必要になるのが契約書です。
自費リハに関係する主な法律と契約形態

自費リハビリサービスは、医療保険や介護保険の制度外で行われるため、提供者と利用者が個別に契約を結ぶ“自由契約”として位置づけられます。
そのため、保険サービスのように国のルールで細かく定められた書式や基準は存在しません。
一見すると自由度が高いように思えますが、実はこの「自由さ」がトラブルの原因になりやすいのです。
☑ 契約形態:多くは「準委任契約」にあたる
自費リハビリの契約は、法律上は「請負契約」ではなく「準委任契約」に該当するのが一般的です。
- 請負契約:成果物(完成)を目的とする契約
- 準委任契約:一定の事務や行為の遂行を目的とし、成果そのものを保証しない契約
リハビリは「一定の行為の提供(施術・運動指導)」を行うものであり、
「治癒」や「改善」という結果を約束する性質のものではありません。
したがって、契約書には次のような表現を明確にしておく必要があります。
例)本サービスは治療行為ではなく、結果を保証するものではありません。
提供者は、善良な管理者の注意をもってサービスを行います。
このように記載しておくことで、サービスの性質を明確化し、
「結果責任(請負)」ではなく、「行為責任(準委任)」として法的リスクを抑えることができます。
☑ 医師法との関係にも注意
リハビリ行為が「医療行為」に該当する場合、医師法第17条に抵触するおそれがあります。
理学療法士や作業療法士などの国家資格者であっても、医師の指示を受けずに治療目的で行為をすることは制限されているため、
契約書上も次のように明示しておくことが望ましいです。
例)本サービスは、医師の治療を補完する目的で行うものであり、診断や治療行為には該当しません。
特に、痛みの治療・神経障害の改善・関節可動域の回復などを明示的にうたう表現は、
医療広告ガイドライン上も注意が必要です。
☑ 消費者保護の観点から適用される法律
自費リハビリは、利用者(個人)と事業者(専門職)との契約となるため、
「消費者契約法」や「特定商取引法」の対象にもなります。
特に留意すべき点は次のとおりです。
| 法律名 | 主な内容 | 自費リハとの関係 |
|---|---|---|
| 消費者契約法 | 不当条項(免責・過大な解約料など)は無効 | 「返金不可」「責任を負わない」等の一方的条項はリスク |
| 特定商取引法 | 勧誘方法・クーリングオフ規制など | 店舗外での契約や高額回数券販売の際に適用可能性あり |
| 景品表示法 | 誇大広告や虚偽表示の禁止 | 「必ず改善」「医療と同等の効果」などの表現はNG |
リハビリをすれば必ず治ると思っている方々はたくさんいます。
リハビリは“結果”ではなく“過程”を提供する契約──この意識を持つだけで、リスクは大きく減ります。
表現があいまいだと争いになる:契約書で明確化すべきポイント

契約書トラブルの多くは、「契約書がなかった」ことよりも、“書いてあるのに意味があいまいだった”ことで起きています。
同じ言葉でも、人によって受け取り方が違うからです。
特に自費リハビリのように、結果や体感に個人差があるサービスでは、あいまいな表現がトラブルの引き金になります。
☑ よくあるあいまい表現の例
- 効果が感じられなかった場合、返金に応じます
「どの程度の効果が出なければ返金対象か」が不明確 - キャンセルは原則前日までに
「当日キャンセル」「連絡なし欠席」などの扱いが不明確 - 体調により中止することがあります
「中止判断」「再開基準」「料金の扱い」が曖昧 - 怪我や事故については一切責任を負いません
消費者契約法8条により無効となるおそれあり
☑ 記載のコツ:具体+基準+理由
契約書の文言は、「何を」「どのように」「なぜそうするのか」を揃えて書くと誤解を防げます。
例:
×「体調が悪い場合は中止することがあります」
○「利用者の体温が37.5℃以上、または感染症の疑いがある場合は、安全確保のため当日の実施を中止します(再開は症状消失後24時間以上経過後とします)」
こうした“基準のある書き方”をしておくと、後で説明責任を果たしやすくなります。
“なんとなく書いてある”では防げない。
契約書は、“どこまでが責任か”を線で引くための道具です。
私がサポートできること

保険外リハビリサービスを安心して始めるためには、「法的に整った書類」と「現場を理解した内容」の両立が欠かせません。
私は理学療法士としての経験を活かし、介護・医療現場の実情を踏まえた実践的なサポートを行っています。
- 自費リハビリに特化した契約書・重要事項説明書の作成
現場で使いやすく、利用者にもわかりやすい内容に仕上げます。 - 利用規約や免責事項の文案作成
万一のトラブルやクレームにも対応できるよう、リスクを最小限に抑える文面を整備します。 - 法令に基づく内容チェック
消費者契約法・民法・個人情報保護法などの観点から、契約内容が法的に問題ないかを確認します。 - 現場運営に即した文面提案
現場の動線や利用者対応の流れを踏まえ、実務で活かせる書類構成をご提案します。
「現場を知る行政書士」だからこそ作れる契約書があります。
法律の理屈だけでなく、実際の運営に役立つ“生きた書類”で、現場を守り、リハビリ業界を支えていきたいと考えています。
安心して自費リハビリを提供するために

契約書は、トラブルを防ぎ、利用者との信頼関係を築くための基本です。
どれだけ技術や想いがあっても、法的な備えがなければ、事業を継続するうえで不安が残ります。
「現場を理解した行政書士」がサポートすることで、リハビリ専門職の皆さまが安心して開業・運営できる環境を整えることができます。
契約書や重要事項説明書の整備を通して、利用者にも安心して選ばれるサービスを一緒に形にしていきましょう。
契約書を作成している弁護士や行政書士は数多くいますが、介護・医療の現場で実際に働いていた行政書士は多くありません。
契約書作りで本当に大切なのは、現場に潜むリスクを具体的に想定し、一つひとつ丁寧に潰していくこと。
法律と現場、両方の視点からサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
契約書のひな型販売リンク↓
※本雛形は一般的なケースを想定して作成したものであり、すべての事案に適合することを保証するものではありません。
※本雛形の使用によって生じた損害やトラブルについて、当事務所は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
※デジタルコンテンツの性質上、決済完了後の返品・返金には応じられません。
📌オンラインの打ち合わせ不要!LINEでのやり取りだけで契約書を作成します!

【平日】09:00~21:00【休日】09:00~18:00
24時間お問い合わせ可能!
確認次第すぐご連絡いたします

