「自費での外出支援サービス」は、買い物・通院・旅行など、日常を支える大切な支援。
しかし、保険サービスのような明確なルールがなく、トラブルが起きやすい分野でもあります。
“どこまで支援するのか”“事故が起きたらどうするのか”をあらかじめ決めておくことが、
お互いの安心を守る第一歩です。
外出支援サービスの法的位置づけ
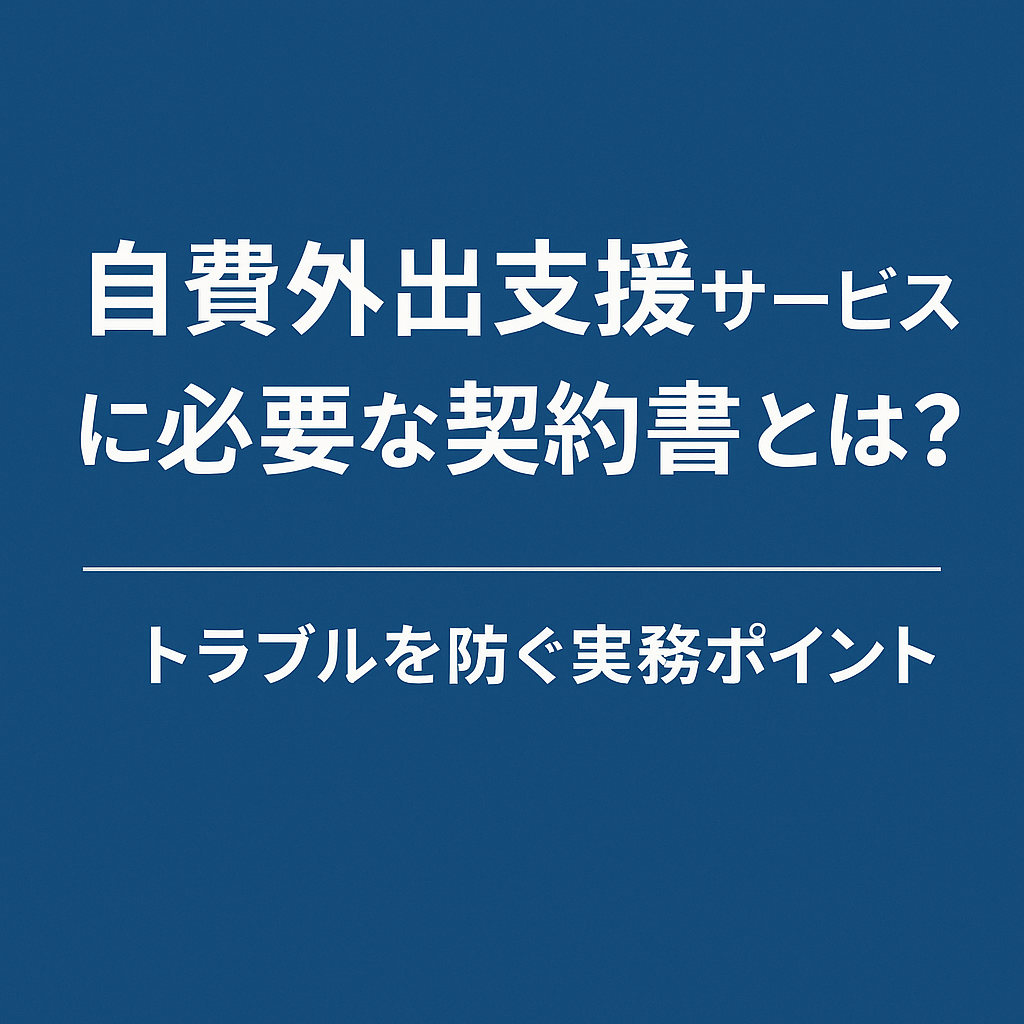
自費による外出支援サービスは、介護保険の枠外で行われる任意契約です。
つまり、国や自治体が定める基準・監査の対象外であり、契約内容そのものがサービス提供のすべての根拠になります。
この契約は法律上、「成果(結果)」を約束する請負契約ではなく、
「一定の行為を適切に行うこと」を目的とした準委任契約に該当します。
外出支援では「目的地に同行する」「安全に配慮して付き添う」といった行為の提供が主であり、
「必ず安全に目的地へ到着する」といった結果の保証は含まれません。
そのため、契約書には、
- どこまでがサービスの範囲か
- 事業者がどのような注意義務を負うのか
- どのような場合に中止・解除できるのか
を明確に定めておくことが重要です。
これらを文書で整理しておくことで、提供者・利用者の双方が安心して外出支援を行える環境を整えることができます。
準委任契約は“結果”ではなく“行為”の約束。トラブルを防ぐには、この違いを理解しておくことが重要です。
トラブルになりやすいポイント
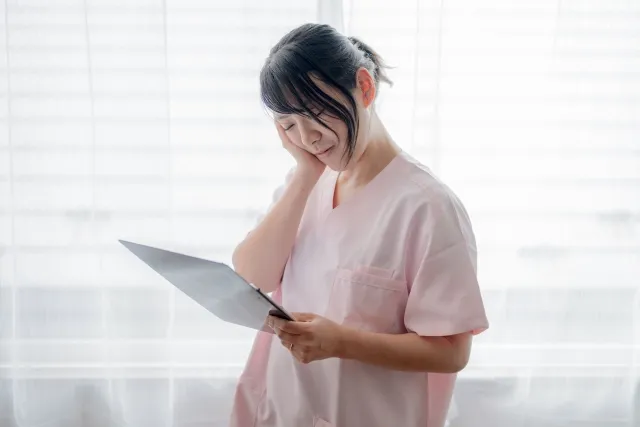
外出支援の現場では、善意から始めたサービスが思わぬトラブルにつながることがあります。
たとえば、
「ここまで送ってもらえると思っていた」
「同乗中に転倒したのは誰の責任か」
「キャンセル料を請求された」
といったケースです。
これらの多くは、サービスの範囲や料金、リスクの線引きが共有されていなかったことが原因です。
外出支援は、介護保険サービスのように細かな基準が定められていないため、
どこまで支援を行い、どこからは自己責任となるのかを、あらかじめ明確にしておく必要があります。
契約書に「サービス範囲」「料金・キャンセル規定」「中止基準」「緊急時の対応」などを具体的に記載することで、
“してあげた”・“してもらった”の思い違いを防ぎ、双方の安心と信頼を守ることができます。
善意の支援ほど、あいまいなままだと誤解が生まれやすいんです。
契約書は、誰が読んでも解釈に違いがでないように工夫をする必要があります。
契約書に入れておくべき5つの項目

外出支援サービスの性質上、事業者と利用者の間で「どこまでやるのか」「どこからは責任外なのか」を明確にしておく必要があります。
最低限、次の5つの項目は具体的に記載しておくことをおすすめします。
☑ サービス内容と範囲
外出支援で行う具体的な内容(送迎・付き添い・代行・見守りなど)を明記します。
「自宅から病院までの移動支援」なのか、「病院内での手続き同行」まで含むのか、
想定している範囲をできるだけ具体的に書くことがポイントです。
☑ 料金・支払い方法・キャンセル規定
1回あたりの料金、支払いのタイミング、当日キャンセル時の扱いを明確にします。
「何日前までなら無料」「当日中止は全額」など、数字で示すことで誤解を防止できます。
☑ 安全配慮と免責の範囲
外出支援中の事故や体調不良など、想定されるリスクに対して、
事業者がどのような注意義務を負うのかを明示します。
「安全に配慮して支援を行うが、結果を保証するものではない」といった
準委任契約としての立場を明確にしておきましょう。
☑ 緊急時の対応
利用中に転倒や発熱が起きた場合の対応方針(救急要請・家族連絡・医療機関搬送の判断)を定めます。
緊急時の連絡先や判断権限を事前に共有しておくことで、混乱や責任の押し付け合いを防げます。
☑ 契約期間と解除条件
契約の開始日・終了日、中途解約や再契約の方法を明記します。
「双方の合意」「書面またはメール通知」など、手続きのルールを具体化しておくと安心です。
“なんとなく書いてある”では防げない。
契約書は、“どこまでが責任か”を線で引くための道具です。
私がサポートできること

自費サービスの契約書は、テンプレートをそのまま使うだけでは不十分です。
サービス内容や現場の運営体制、対象者の特性によって、
「どこまで支援するか」「どこから責任を負うか」の線引きは変わってきます。
私は、現場を理解している行政書士として、
介護・医療の実情に即した契約書の作成や文面の調整を行っています。
単に法律的に正しいだけでなく、実際の運用に耐えられる内容にすることを大切にしています。
- サービス内容や料金の説明文書(重要事項説明書)
- 同意書・免責事項・感染症時の対応基準(別紙様式)
など、契約書とあわせて整備すべき関連書類の作成もサポート可能です。
自費外出支援・自費リハビリといった「制度に縛られない支援」を安心して続けていくために、
契約書を通して信頼と安全のしくみを整えるお手伝いをいたします。
「現場を知る行政書士」だからこそ作れる契約書があります。
法律の理屈だけでなく、実際の運営に役立つ“生きた書類”で、現場を守る契約書づくり、それが私の専門です。
安心して外出支援を提供するために

契約書は、トラブルを防ぎ、利用者との信頼関係を築くための基本です。
どれだけ想いがあっても、法的な備えがなければ、事業を継続するうえで不安が残ります。
「現場を理解した行政書士」がサポートすることで、皆さまが安心して開業・運営できる環境を整えることができます。
契約書の整備を通して、利用者にも安心して選ばれるサービスを一緒に形にしていきましょう。
契約書を作成している弁護士や行政書士は数多くいますが、介護・医療の現場で実際に働いていた行政書士は多くありません。
契約書作りで本当に大切なのは、現場に潜むリスクを具体的に想定し、一つひとつ丁寧に潰していくこと。
法律と現場、両方の視点からサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
📌オンラインの打ち合わせ不要!LINEでのやり取りだけで契約書を作成します!

【平日】09:00~21:00【休日】09:00~18:00
24時間お問い合わせ可能!
確認次第すぐご連絡いたします

